僕が記憶を遡り、掘り返す事が出来る「最初の記憶」は、幼稚園児辺りの未就学時代だ。
正直、その頃から「良い記憶」というモノは少ない。
その頃の「僕の家庭」は、まだ壊れてはいなかった。
けれども、僕の「母に愛されているだろうか?という不安」や「兄に対する恐怖」は、この頃から始まっていた。

今思えば、「その後に繋がる家庭問題アリアリな家庭」だったんだと思う。
だけど、それでも、まだ「マシ」な頃だったと思う。
目次
最初の記憶。
「偽」シティボーイ
僕は東京で生まれた。
生まれてから小学校に入学する辺りまでを東京で過ごす事になる。
僕が住んでいた場所は、少し歩けば「歌舞伎町」に入る様な繁華街に近い場所にあった。
住んでいたマンションの隣りの部屋では「発砲事件」が起きたりと、お世辞にも「治安が良い」とは言えない土地だった。

他にも、ごく近所の「お城」だと思って遊んでいた場所は「ラブホテル」で、「んなトコで遊ぶんじゃあねえ!」と、両親に叱られたのは良い思い出だ。
そんな僕は、出身地を聞かれると「こう」答える。
チッタ「出身地は東京です!!」
尚、僕は東京には7年しか住んでいない。
「不安を与えた」両親の記憶
僕の父は、駅前の「ラーメン屋」で働いていた。
そして母は、「配達関係?」のパートをしていた。
正直、当時の「父の記憶」は薄い。
両親の記憶で残っているのは、「母との記憶」だけだ。
母は基本、僕を家に置いてパートへ行った。

尚、当時の僕は「幼稚園児」か、そこらである。
「家にひとりで置かれた記憶」があるあたり、もしかしたら「幼稚園児以前の記憶」なのかもしれない。
まぁとにかく、そんな僕をひとりにしてパートに出る母親だった。
「家にひとりで置かれた僕」は不安だったのだろう。
純粋に「ひとりで置かれた」不安。
「カーさんに必要とされていないんじゃないか?」という不安。
そんな「不安」を抱えていたんだと思う。
そんな僕は、昼寝をしていたのか「母が帰ってくる夢」ばかり見ていた。
というか、「夢と現実」がごちゃ混ぜになり、「カーさんが帰って来たのに、カーさんがいない。」「なんだコレ?」と混乱していた。
そして僕は、なぜか「カーテンに隠れて」うんこしていた。
そんな記憶がある。
そしてもうひとつ、「母の記憶」で印象深いモノがある。
「母に抱きしめられている」記憶だ。
僕はその頃、「チッタが生まれて良かった?」と、しょっちゅう母に聞いていた。
僕の問いに、母は「うん、良かったよ。」と、抱きしめてくれたんだ。

僕は「それ」が、凄く嬉しかった。
「嬉しい気持ち」が強く、「もっと好かれる様になろう。」と、子供ながらに考えていたのを覚えている。
「恐怖を与えた」兄の記憶
実は、「僕の最初の記憶」は「住んでいた場所」でもなく「両親の記憶」でもない。
「兄の記憶」だ。
僕が過去を振り返り、「最も初めの記憶」を掘り返した時に出てくるのは「兄の記憶」だ。
僕に向ける、兄の「憎しみに満ちた」顔。
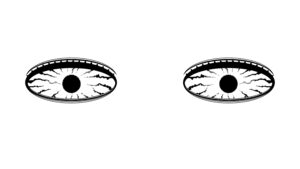
それが僕の「最初の記憶」だ。
と言うか、僕の「子供の頃の記憶」は、ほとんどが「兄の記憶」だ。
幼い僕は「兄に嫌われている事」を、なんとなく理解していた。
兄は、とにかく僕に「当たり」が強い。
「僕が何をしても」「僕が何をしなくても」兄は怒る。

「怒る」といっても、当時の兄は「癇癪を起こす」程度のモノだったが、当時の僕には凄く怖かったモノだったのを覚えている。
だけど、僕は兄から離れなかった。
それは何故か。
母が喜ぶからだ。
「兄の機嫌が良いと、母が喜ぶ。」
この事を「無意識」に理解していた様に思う。
カーさん「チッタはニーちゃんと仲良く出来てえらいね。」
こうやって母が喜び、褒めてくれるのを「愛情だ。」と誤認していたんだろう。
つまり、「チッタは必要だよ。」と、母に言ってもらいたかったんだと思う。
しかし、当然の事ながら「幼稚園児の僕のご機嫌取り」なんざ、ほとんどが失敗に終わる。
ほとんどが「兄の癇癪」という恐怖の結果な訳だ。
だけど僕は、「10中の1回の成功」を求めていたんだと思う。

だから僕は兄にくっついて廻った。
だから「僕の最初の記憶」は、ほとんどが「兄に怒られる恐怖」ばかりだ。
本当は怖いんだけれど。
僕にとっての「兄」という存在。
僕の生い立ちを語るにあたって、兄の存在は必要不可欠だ。
兄との関係は、「兄弟」という括りだけでは済まない。
僕にとっての「兄」という存在は、「憎しみの対象」であり、「恐怖の対象」である。
その気持ちは、今でも完全には消えていない。
あの頃はまだ、「憎しみの対象」ではなかったと思う。
だけど、幼稚園児そこそこの僕には、既に兄は「恐怖の対象」になっていた。
兄の僕に対する虐待は、「僕の自我が芽生える以前」から始まっていた。

自我が芽生えた頃には、僕にとっての兄は「危険対象」であり、「恐怖の対象」だ。
「僕が育った家庭」は、僕にとって、自我が芽生える以前から「安全地帯」ではなかった。
「恐怖の対象」から逃げる事が出来ない理由。
仮に、「人間に対して、敵意剥き出しのライオン」が檻に入っていたら、みなさんはどうするだろうか?

ほとんどの人は「近づかない」という選択をすると思う。
極論を言ってしまえば、「僕の家」には「そのライオンが入った檻が置かれている」状況と同じだ。
本来なら僕だって、そんなオッカねえモンに近づきたくない。
だけど僕は、「そのライオン」に近づき続けた。
時には引っ掛れ、噛みつかれて、痛い思いをしながらも近づく。
敵意剥き出しの威嚇をされ、恐い思いを無視しながらも近づく。
そんな「嫌な思い」をしてまで近づき続けたのは、母に「チッタは良い子だね。」と褒めてもらいたかったからだろう。
しかしまぁ、なんと「非合理的な方法」だろうか。
「母に褒められたい」「愛されている確証が欲しい」のなら、他にも方法があったはずだ。
まぁ、多分、「思いつく限りの他の方法」も試した上での行動なのだろう。
「母の愛情をもらえる可能性のある行動は、なんでもやろう。」
それくらい「母の愛情」に飢えていたんだと思う。
だから、怖い思いをしてまで兄のご機嫌取りをしたんだと思う。
だから、「恐怖の対象から逃げられなかった」んだと思う。
「不安」と「恐怖」の記憶。
僕が幼稚園児かそこらの未就学時代。
「あの家」での記憶は、「不安」と「恐怖」でいっぱいだった。
母からは「純粋な不安」と、「愛されていない、必要とされていないんじゃないか?」という不安。
兄からは「敵意と憎しみに満ちた顔」による恐怖。
そんな「不安」と「恐怖」でいっぱいだった。

そして僕が「不安を避ける」為に選んだ行動が「恐怖を避けない」というモノだった。
僕は、「不安も恐怖も無い家庭で育った人」ってのには、「羨ましい」と思う気持ちが確かにある。
だけど、「あの家で育った僕」には、そんなモノは「無いモノねだり」でしかない。
あの頃の、あの家には、「不安と恐怖の記憶」ばかりだ。
「あの家で育った僕」には「不安」と「恐怖」と付き合っていくしかなかった。



完全にセルフカウンセリングだね。
よくぞここまで言語化して、客観視したねー。大事な事だよねー。
ハンターハンターの団長の言葉を思い出します。
自分に娘が出来て子育てしてて思うけど、子供ほったらかしでパート行くのは、どうかしてる。
家計的に仕方なかったのかもだし、人の親だから悪く言いたくないがね😅
おばさん自身もそういう境遇で育てられて、それが当たり前と思っちゃてたのかもね。
「動機の言語化か…。大好きです!!」
自分を掴むカギはそこにあるのよ!!
本当、カーさんは頭のネジが飛んでると思う。
だけど、カーさんの事情を考慮すると、確かにカーさんひとりを責めるには酷な事情があったと思う。
だけど、当時の自分の不安だった気持ち、ツラかった思いってのは、一生忘れずに取っておく。
その上でカーさんの事情を考慮しても憎む気持ちがあるのなら、存分に憎めば良いと思ってる。
今のところ、憎しみ(とは少し違うかな?)がないわけじゃないけど、同情はしてる。